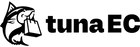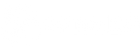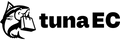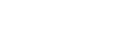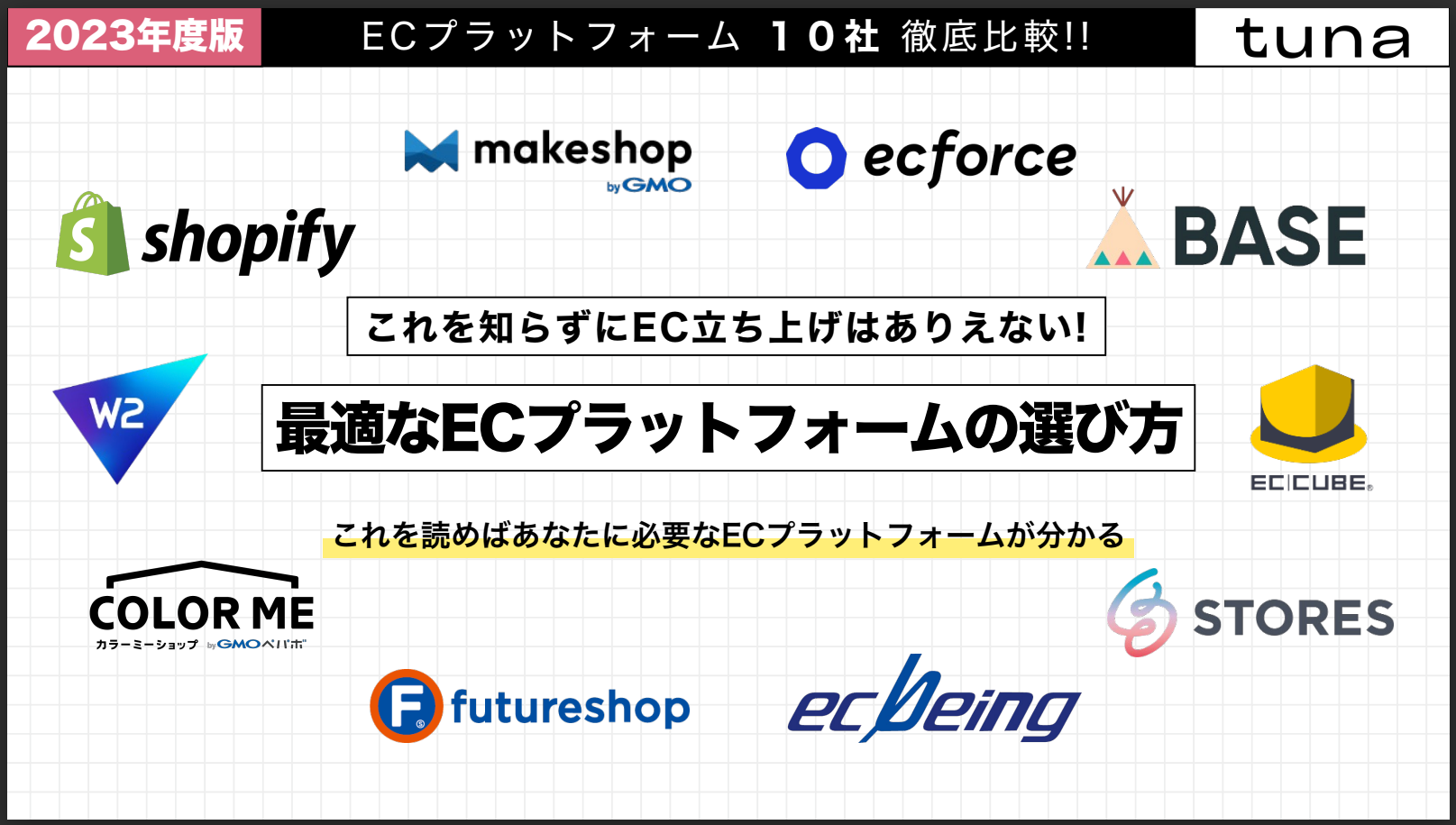Shopifyの在庫管理を徹底解説!基本的な方法から複数拠点・外部との在庫連携まで

Shopifyでのストア運営を始めたものの、在庫の数が合わなくて困った経験はありませんか。「実店舗とECサイトで在庫数がずれてしまい、お客様に迷惑をかけてしまった」「在庫があるはずなのに、なぜか販売機会を逃してしまった」など、Shopifyの在庫管理に関する悩みは尽きないものです。
特に、取り扱う商品数が増えたり、実店舗や他のECモールといった複数の販売チャネルを持ち始めたりすると、手作業での在庫管理には限界が訪れます。その結果、売り越しによるクレームや、欠品による機会損失が頻発し、ビジネスの成長を妨げる大きな原因になりがちです。
Shopifyに標準で備わっている基本的な在庫管理の方法から、事業の成長に不可欠となる複数拠点や外部サービスとの効率的な在庫連携まで、あなたのストアの段階に合わせた最適な管理手法を見つけるための知識を網羅的に解説します。
{CON_TITLE}この記事の結論{/CON_TITLE} {CON_BODY} - Shopifyの標準機能だけで、リアルタイムの在庫追跡や複数ロケーションでの基本的な在庫管理が可能です。 - 実店舗や複数のECサイトを運営する場合、売り越しや機会損失を防ぐために「在庫連携」が不可欠になります。 - 在庫連携を実現するには「Shopifyアプリ」「外部システムとの連携」「APIによる独自開発」の3つの方法があります。 - ツールの導入だけでなく、定期的な棚卸しや適正在庫の基準設定といった運用ルールを定めることが成功の鍵です。 {/COL_BODY}Shopifyの在庫管理とは?標準機能でできること
Shopifyの在庫管理と聞くと、何か特別なアプリが必要だと考える方もいるかもしれません。
しかし、Shopifyには追加費用なしで利用できる、非常に強力な在庫管理機能が標準で備わっています。
まずは、この標準機能で何ができるのかを正しく理解することが、効率的なストア運営の第一歩です。
リアルタイムでの在庫追跡
Shopifyの最も基本的な在庫管理機能は、リアルタイムでの在庫追跡です。
商品に対して在庫追跡を有効にすると、注文が入るたびに在庫数が自動的に減少します。
また、注文がキャンセルされたり、返品処理が行われたりした場合には、在庫数を自動で元に戻す設定も可能です。
これにより、手作業で在庫を更新する手間が省け、人為的なミスを大幅に削減できます。
複数ロケーション(拠点)での在庫管理
Shopifyでは、「ロケーション」という機能を使って、複数の拠点にある在庫を一元管理できます。
例えば、本社倉庫、支社の倉庫、実店舗など、物理的に異なる場所にある在庫をそれぞれ登録し、どのロケーションから商品を発送するかを設定することが可能です。
これにより、実店舗とECサイトの両方を運営している場合でも、Shopifyの管理画面一つで全体の在庫状況を正確に把握できます。
在庫履歴の確認
「いつの間にか在庫数が合わなくなっている」という事態を防ぐために、在庫履歴の確認機能は非常に重要です。
Shopifyでは、特定の商品について、いつ、誰が、どのような理由で在庫数を調整したのかの履歴をすべて確認できます(例:注文、手動調整、アプリによる更新など)。
在庫数に差異が生じた際に原因を素早く特定できるため、管理体制の改善にも役立ちます。
Shopifyの標準機能で行う基本的な在庫管理の方法
それでは、実際にShopifyの管理画面で在庫を管理するための基本的な操作方法を見ていきましょう。
ここでは、在庫管理を始める上で必須となる4つのステップを解説します。
これらの操作を覚えるだけで、日々の在庫管理業務は格段にスムーズになります。
1. 商品の在庫追跡を有効にする設定
Shopifyで在庫管理を始めるには、まず商品ごとに在庫追跡を有効にする必要があります。
設定は非常に簡単です。
- Shopifyの管理画面から「商品管理」に移動し、対象の商品を選択します。
- 商品詳細ページの中ほどにある「在庫」セクションで、「在庫を追跡する」のチェックボックスをオンにします。
- 在庫数を入力する欄が表示されるので、現在の在庫数を入力し、保存します。
この設定を行うことで、その商品はShopifyの在庫管理システムの対象となります。
2. 在庫数を手動で調整する方法
商品が入荷した際や、棚卸しで実際の在庫数とデータに差異が見つかった場合には、手動で在庫数を調整します。
管理画面の「商品管理」から「在庫」ページにアクセスすると、登録されているすべての商品の在庫数を一覧で確認・編集できます。
変更したい商品の「在庫数」の数値を直接クリックして新しい数量を入力し、「保存」するだけで更新が完了します。
急な在庫変動にも迅速に対応できる、基本的な操作です。
3. CSVファイルで在庫情報を一括更新する方法
取り扱う商品数が多くなると、一つひとつの商品を個別に更新するのは大変な作業です。
そのような場合は、CSVファイルを使って在庫情報を一括で更新する方法が便利です。
まず、「在庫」ページから現在の在庫情報をCSVファイルとしてエクスポート(出力)します。
次に、ダウンロードしたCSVファイルをExcelなどの表計算ソフトで開き、在庫数を編集します。
編集が完了したら、同じく「在庫」ページからそのCSVファイルをインポート(取り込み)することで、すべての商品の在庫情報が一括で更新されます。
|
【実践Tips】CSVでの在庫一括更新、よくある失敗と注意点 CSVでの一括更新は非常に便利ですが、いくつか注意点があります。特に初心者が陥りがちな失敗を防ぐために、以下のポイントを押さえておきましょう。
これらの点に気をつけるだけで、CSV更新の成功率は格段に上がります。 |
【効率化の鍵】Shopifyにおける在庫連携の重要性
Shopifyの標準機能は非常に優秀ですが、事業が拡大し、販売チャネルが複雑化してくると、それだけでは対応しきれない課題が出てきます。
そこで重要になるのが「Shopifyの在庫連携」という考え方です。
これは、Shopifyと他のシステム(実店舗のPOSレジ、他のECモールなど)の間で在庫情報を自動的に同期させる仕組みを指します。
在庫連携が必要になる主なケース
Shopifyでの在庫連携は、特に以下のようなケースでその真価を発揮します。
- 実店舗とECサイトを運営している:実店舗で商品が売れた際に、ECサイトの在庫も自動で減らす必要があります。逆も同様で、ECサイトで売れたら実店舗の在庫情報に反映させなければなりません。
- 複数のECサイトを運営している:Shopifyに加えて、楽天市場やAmazonなど、複数のECモールに出店している場合、すべてのチャネルの在庫を一元管理する必要があります。
- 外部の倉庫サービスを利用している:自社で在庫を持たず、外部の物流倉庫(3PL)に在庫管理と発送を委託している場合、倉庫の在庫システムとShopifyを連携させる必要があります。
これらのケースで手動管理を続けると、いずれ在庫のズレや管理コストの増大といった問題に直面します。
在庫連携で解消できる課題(売り越し・機会損失の防止)
在庫連携を導入する最大のメリットは、「売り越し」と「機会損失」という二大課題を解消できる点にあります。
例えば、ある商品の在庫が残り1点だったとします。
在庫連携がなければ、実店舗とECサイトでほぼ同時にその商品が売れてしまい、「売り越し」が発生する可能性があります。
これは顧客満足度の低下に直結します。
逆に、ECサイトで在庫切れになっていても、実は実店舗には在庫が残っているかもしれません。
この場合、本来売れるはずだった商品が売れない「機会損失」が発生してしまいます。
Shopifyでの在庫連携は、すべての販売チャネルの在庫情報をリアルタイムで同期することで、こうした問題を根本的に解決します。
Shopifyで在庫連携を実現する3つの方法
では、具体的にShopifyで在庫連携を実現するには、どのような方法があるのでしょうか。
事業の規模や予算、技術的な要件に応じて、主に3つのアプローチが考えられます。
それぞれの特徴を理解し、自社に最適な方法を選択することが重要です。
1. Shopifyアプリを活用する
最も手軽で一般的な方法が、Shopify App Storeで提供されている在庫管理・連携アプリを利用することです。
これらのアプリをインストールするだけで、他のECモールやPOSレジシステムとShopifyの在庫情報を簡単に同期させることができます。
多くのアプリは月額制で、比較的低コストから始められるのが大きなメリットです。
プログラミングの知識も不要なため、まずはスピーディーに在庫連携を試してみたいという事業者の方に最適な選択肢と言えるでしょう。
2. 外部の在庫管理システムと連携する
より本格的な在庫管理を行いたい場合や、取り扱う商品数が非常に多い大規模な事業者には、外部の専門的な在庫管理システム(WMS:倉庫管理システムなど)を導入し、Shopifyと連携させる方法があります。
これらのシステムは、在庫管理だけでなく、入出荷管理やロケーション管理、ハンディターミナルを使ったピッキングなど、物流業務全体を効率化する高度な機能を備えています。
初期費用や月額費用はアプリに比べて高額になりますが、大規模なビジネスの根幹を支える強固な基盤を構築できます。
3. APIを利用して独自にシステムを開発する
既存のアプリやシステムでは対応できない、特殊な要件がある場合には、Shopifyが提供するAPI(Application Programming Interface)を利用して、独自の連携システムを開発するという選択肢もあります。
例えば、自社独自の基幹システムや生産管理システムと在庫情報を連携させたい場合などがこれにあたります。
開発には専門的な知識とコストが必要になりますが、自社の業務フローに完全に合致した、最も自由度の高い在庫連携を実現できるのが最大のメリットです。
Shopifyの在庫管理を成功させるためのポイント
最適なツールやシステムを導入したとしても、それだけではShopifyの在庫管理は成功しません。
日々の運用の中で、データの精度を高く保つためのルール作りや習慣が不可欠です。
ここでは、在庫管理を成功に導くための3つの重要なポイントを解説します。
定期的な棚卸しで実在庫との差異をなくす
どれだけ優れたシステムを導入しても、紛失や破損、入力ミスなどにより、データ上の在庫数と実際の在庫数(実在庫)には少しずつ差異が生まれてしまいます。
この差異を放置すると、売り越しや機会損失の原因となります。
これを解消するために、最低でも半年に一度、できれば四半期に一度など、定期的に「棚卸し」を行いましょう。
すべての商品の実在庫を数え、システム上のデータと照合して修正する地道な作業ですが、在庫管理の精度を維持するためには絶対に欠かせないプロセスです。
適正在庫の基準を明確にする
在庫管理の目的は、単に数を合わせることだけではありません。
欠品による機会損失を防ぎつつ、過剰在庫によるキャッシュフローの悪化も避ける「適正在庫」を維持することが重要です。
過去の販売データや季節変動などを分析し、「この商品は最低でも何個、最大でも何個まで在庫を持つ」といった基準を商品ごとに設定しましょう。
この基準があれば、発注のタイミングや数量を感覚ではなくデータに基づいて判断できるようになり、より健全なストア運営が可能になります。
返品や予約販売の在庫管理フローを決めておく
日々の運用では、注文と出荷以外にも在庫が変動するイレギュラーなケースが発生します。
特に見落としがちなのが「返品」と「予約販売」です。
返品された商品を在庫に戻す際のルール(検品は誰がするか、どのタイミングで在庫に反映させるかなど)を明確にしておかないと、不良品が再販されたり、在庫への反映が漏れたりする可能性があります。
また、予約販売を行う場合は、入荷前の在庫をどのように管理し、通常販売の在庫と区別するかといったフローを事前に決めておくことがトラブル防止につながります。
まとめ:自社に合った在庫管理でShopifyストアの成長を加速させよう
この記事では、Shopifyの在庫管理について、標準機能でできる基本的な方法から、事業拡大に欠かせない在庫連携の重要性、そして運用を成功させるためのポイントまでを網羅的に解説しました。
Shopifyの在庫管理は、ストアの信頼性と収益性に直結する非常に重要な業務です。
まずはShopifyの標準機能を最大限に活用し、基本的な在庫管理のプロセスを確立することから始めましょう。
そして、実店舗との連携や多店舗展開など、事業が次のステージに進む際には、本記事で紹介した在庫連携の方法を参考に、自社の規模や状況に最適なソリューションを検討してみてください。
適切な在庫管理体制を構築することが、あなたのShopifyストアの成長をさらに加速させる力強い土台となるはずです。
ECサイトの構築にはECプラットフォームが欠かせません。こちらの資料では合計10社のプラットフォームの導入費用や機能について簡単に比較できるようにまとめました。
これからECサイトの構築やリプレイスを検討されているご担当者様は、こちらのボタンからECカオスマップ資料をダウンロードいただき、ぜひ比較検討にお役立てください!