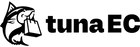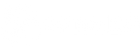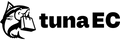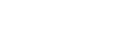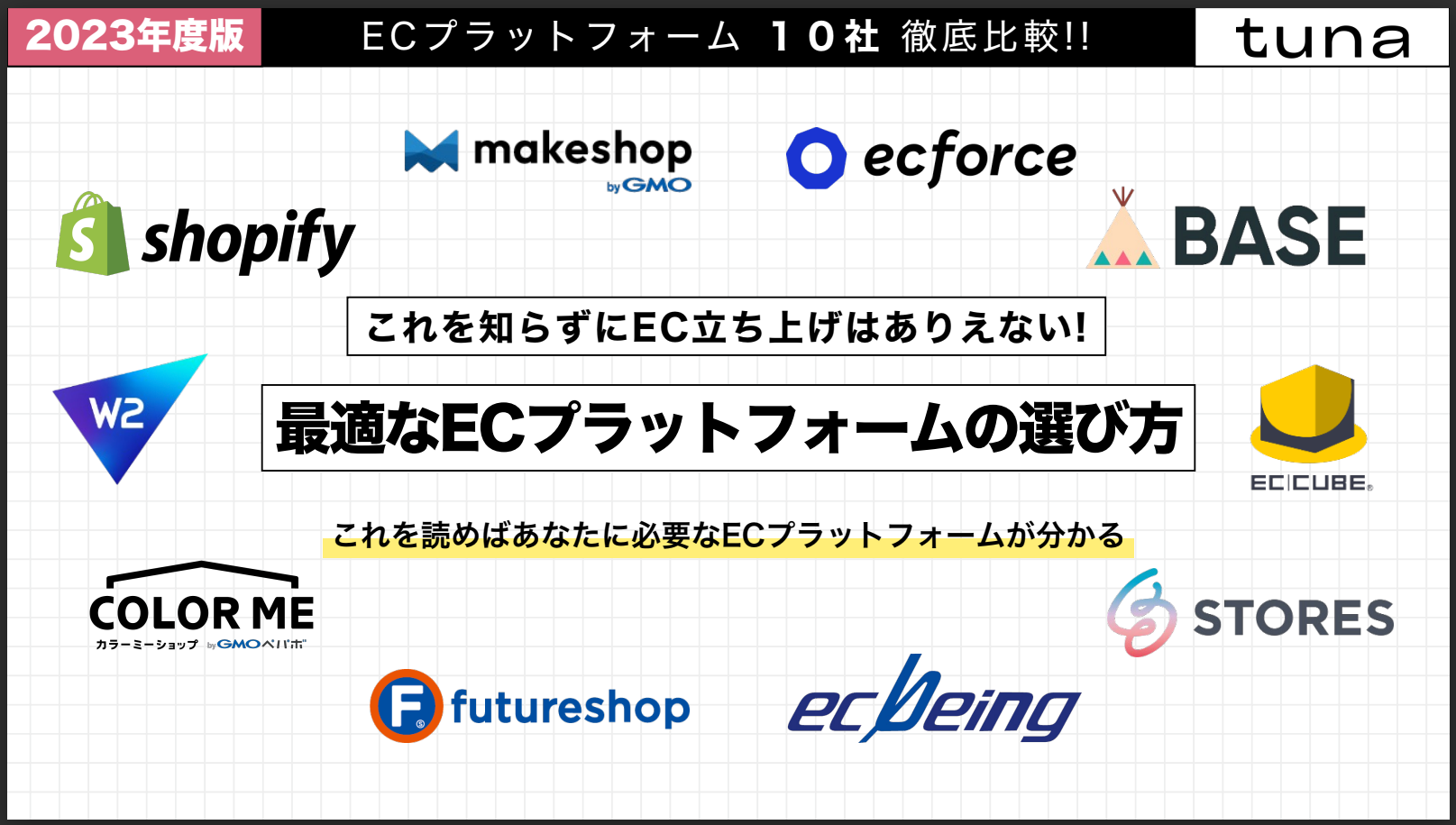Shopifyの決済方法はどれがいい?手数料で損しないための最適な選び方と設定手順

Shopifyでネットショップを立ち上げる際、「決済方法は何を導入すればいいのだろう?」「手数料が複雑で、結局トータルでいくらかかるのか分からない…」といった疑問や不安を感じていませんか。お客様にとって使いやすい支払い方法を用意しないと、せっかくの販売機会を逃してしまうのではないか、という懸念は多くの運営担当者が抱える悩みです。
その背景には、Shopifyの決済システムが持つ独自の構造があります。特に、基本となる「Shopifyペイメント」と、選択肢を広げる「外部決済サービス」の関係性、そして後者を利用する際に発生する「取引手数料」という見えにくいコストの存在が、担当者を混乱させがちです。だからこそ、表面的な手数料率だけで判断してしまうと、気づかぬうちに利益を圧迫してしまうことになりかねません。
Shopify決済の基本構造から、手数料で損しないための合理的な選び方、そして顧客層を広げる決済手段の種類まで、あなたのストアの売上を最大化するための意思決定に必要な情報を網羅的に解説します。
|
この記事の結論 まずは基本の「Shopifyペイメント」を有効化し、主要なクレジットカード決済に迅速に対応しましょう。 |
Shopify決済の基本構造|まず理解すべき2つの仕組み
Shopifyで利用できる決済方法は、大きく分けて2つのカテゴリーに分類されます。
それは、Shopifyが公式に提供する「Shopifyペイメント」と、それ以外の「外部決済サービス」です。
この2つの関係性と、コスト計算で最も重要になる「取引手数料」の仕組みを理解することが、最適な決済方法を選ぶための第一歩です。
1. 基本の「Shopifyペイメント」
Shopifyペイメントは、Shopifyアカウントを開設すれば簡単な設定だけですぐに利用開始できる、公式の決済サービスです。
主要なクレジットカード決済(Visa, Mastercard, American Expressなど)に標準で対応しており、多くのストアにとって決済システムの基盤となります。
特別な理由がない限り、まずはこのShopifyペイメントを有効化するのが基本戦略です。
2. 選択肢を広げる「外部決済サービス」
外部決済サービスは、Shopifyペイメントだけではカバーできない多様な支払いニーズに応えるための選択肢です。
例えば、Amazon Pay、あと払い決済(Paidyなど)、コンビニ決済、銀行振込、スマホ決済(PayPayなど)がこれにあたります。
これらの決済手段を導入することで、クレジットカードを持たない若年層や、オンラインでのカード利用に抵抗がある顧客層にもアプローチでき、販売機会の損失を防ぎます。
【重要】コスト計算の鍵となる「取引手数料」とは?
ここが最も重要なポイントです。Shopifyでは、Shopifyペイメント以外の外部決済サービスを利用して売上が発生した場合、Shopifyに対して「取引手数料」を支払う必要があります。
この手数料は、利用している料金プランによって異なり、以下の通り設定されています。
- ベーシックプラン: 2.0%
- スタンダードプラン: 1.0%
- プレミアムプラン: 0.5%
つまり、外部決済サービスを導入する際は、そのサービス自体が設定している決済手数料に加えて、Shopifyの取引手数料が「上乗せ」で発生するのです。
一方で、Shopifyペイメントを利用した決済では、この取引手数料は一切かかりません。この二重構造を理解しておくことが、正確なコスト比較の前提となります。
まずは導入必須!Shopifyペイメントを徹底解説
結論から言うと、Shopifyでストアを運営するなら、Shopifyペイメントの導入は必須と考えるべきです。
設定が簡単で、多くのメリットがあるため、決済方法選びのスタートラインとなります。
ここでは、Shopifyペイメントの具体的なメリット・デメリット、そして対応している決済の種類と手数料について詳しく見ていきましょう。
Shopifyペイメントを利用する3つのメリット
Shopifyペイメントを導入すべき理由は主に3つあります。
-
取引手数料が無料になる
最大のメリットは、前述の「取引手数料」が一切かからない点です。外部決済サービスで発生する0.5%〜2.0%のコストを削減できるため、利益率に直結します。 -
設定が簡単ですぐに始められる
外部の決済代行サービスのように、複雑な契約や技術的な設定は不要です。Shopifyの管理画面から数ステップで有効化でき、すぐにクレジットカード決済の受付を開始できます。 -
売上管理が一元化できる
すべての取引がShopifyのダッシュボード上で管理されるため、売上金の確認や返金処理が非常にスムーズです。複数の管理画面を行き来する必要がなく、運用工数を大幅に削減できます。
知っておきたいデメリットと注意点
多くのメリットがある一方で、いくつか注意点も存在します。
-
利用には審査がある
Shopifyペイメントを有効化する際には、ストア情報や取扱商品に基づいた審査が行われます。特定の商材(医薬品や金融サービスなど)は利用規約で禁止されているため、事前に確認が必要です。 -
チャージバックのリスク
クレジットカードの不正利用などにより、顧客が支払いを拒否する「チャージバック」が発生するリスクがあります。チャージバックが認められると、事業者は売上金を失うことになります。
|
チャージバック対策の鍵「3Dセキュア」とは? チャージバックは事業者にとって大きなリスクですが、Shopifyペイメントは「3Dセキュア」という本人認証サービスに標準で対応しており、このリスクを軽減できます。 3Dセキュアは、カード決済時にパスワードや生体認証などを追加で要求することで、なりすましによる不正利用を防ぐ仕組みです。 3Dセキュアで認証された取引で不正利用によるチャージバックが発生した場合、その責任がカード発行会社に移転される「ライアビリティシフト」が適用されることがあります。これにより、事業者は売上損失のリスクから守られます。 |
対応しているクレジットカード決済の種類と手数料一覧
Shopifyペイメントでは、以下の主要なクレジットカードブランドに対応しています。
決済手数料は、利用しているShopifyの料金プランによって異なります。
| プラン | 国内発行カードの手数料 | 海外発行カード / Amexの手数料 |
|---|---|---|
| ベーシック | 3.4% | 3.9% |
| スタンダード | 3.25% | 3.85% |
| プレミアム | 3.15% | 3.75% |
※上記に加えて、JCBの決済手数料はプランに関わらず3.95%です。
失敗しないShopify決済方法の選び方【意思決定3ステップ】
Shopifyペイメントを基本としつつ、どの外部決済サービスを追加すべきか。この問いに答えるためには、感覚で選ぶのではなく、論理的な思考フレームワークに沿って検討することが重要です。
ここでは、自社に最適な決済方法の組み合わせを導き出すための「意思決定3ステップ」を紹介します。この手順を踏むことで、自信を持って決済方法を選び、社内での説明もスムーズに行えるようになります。
ステップ1. ターゲット顧客層に合わせた決済手段を考える
最初のステップは、自社の製品やサービスを誰に届けたいのか、つまりターゲット顧客の視点に立つことです。
顧客が普段利用している、あるいは利用したいと思っている決済方法を提供できなければ、購入の最終段階で離脱(カゴ落ち)してしまう可能性が高まります。
実際に、ある調査ではECサイトで希望する決済手段がない場合、54.2%ものユーザーが購入をやめてしまうというデータもあります。
- 若年層がターゲットの場合:クレジットカードを持っていない層も多いため、「あと払い決済」や「コンビニ決済」「スマホ決済」は非常に有効です。
- 高額商品を扱う場合:一括での支払いに抵抗がある顧客向けに、分割払いに対応した「あと払い決済」が購入の後押しになります。
- 幅広い年齢層がターゲットの場合:オンラインでのカード決済に不安を感じる層もいるため、「銀行振込」や「コンビニ決済」といった選択肢を用意すると安心感を与えられます。
まずは顧客の顔を思い浮かべ、彼らが最もスムーズに支払いできる方法は何かを考えることから始めましょう。
ステップ2. トータルコスト(決済手数料+取引手数料)を比較する
次に、導入候補となる外部決済サービスのコストを比較検討します。
ここで絶対に忘れてはならないのが、Shopifyの「取引手数料」です。各決済サービスが提示する手数料率だけを見て判断してはいけません。
必ず以下の式で「トータルコスト」を算出し、比較してください。
トータルコスト = 各決済サービスの決済手数料 + Shopifyの取引手数料(0.5%〜2.0%)
例えば、ベーシックプラン(取引手数料2.0%)を利用していて、決済手数料3.6%の外部決済サービスを導入した場合、顧客がその支払い方法を選ぶたびに、売上の5.6%が手数料としてかかる計算になります。このトータルコストを正確に把握し、事業の利益計画と照らし合わせることが不可欠です。
ステップ3. 運用工数と入金サイクルを確認する
最後に、導入後の運用面も忘れずにチェックしましょう。特に重要なのが「運用工数」と「入金サイクル」です。
- 運用工数:複数の外部決済サービスを導入すると、それぞれの管理画面で売上を確認したり、入金管理をしたりする必要が出てくる場合があります。経理担当者の業務が煩雑にならないか、事前に運用フローを確認しておくことが大切です。
- 入金サイクル:決済サービスによって、売上が自社の口座に入金されるまでの期間(入金サイクル)は様々です。「月末締め・翌月末払い」や「週次払い」など、サービスごとに異なります。このサイクルが遅いと、キャッシュフローが悪化する可能性があるため、特に事業の立ち上げ期には注意が必要です。
手数料の安さだけで選んでしまうと、後々の運用で思わぬ手間や資金繰りの問題が発生することがあります。持続可能なストア運営のために、必ずこのステップも確認しましょう。
顧客層を広げる代表的な外部決済サービスの種類
Shopifyペイメントだけではリーチしきれない顧客層を獲得するために、どのような外部決済サービスが有効なのでしょうか。
ここでは、代表的な決済サービスの種類と、それぞれがどのような顧客に響くのかを解説します。
Amazon Pay|カゴ落ち対策に効果的なID決済
Amazon Payは、顧客が普段利用しているAmazonアカウントに登録された配送先情報とクレジットカード情報を利用して、簡単に支払いができる決済サービスです。
最大のメリットは、購入者が面倒な個人情報やカード情報を新たに入力する必要がない点です。これにより購入手続きが大幅に簡略化され、カゴ落ち率の改善に大きく貢献します。多くのネット利用者が持つAmazonアカウントを活用できるため、幅広い顧客層に有効な決済手段です。
後払い決済 (BNPL)|購入ハードルを下げて若年層に訴求
後払い決済(BNPL: Buy Now, Pay Later)は、顧客が商品を受け取った後に、コンビニや銀行で代金を支払うことができるサービスです。
クレジットカードを持っていない、あるいは利用に抵抗がある若年層に特に人気の支払い方法です。また、「商品を実際に見てから支払いたい」というニーズにも応えられます。高額な商品でも分割払いが可能なサービスもあり、購入の心理的ハードルを下げる効果が期待できます。
コンビニ決済・銀行振込|幅広い顧客層をカバー
昔からある定番の決済方法ですが、今でも根強いニーズがあります。
特に、オンラインでのクレジットカード決済に慣れていない、あるいはセキュリティ面で不安を感じる顧客層にとっては、安心できる支払い方法です。全国のコンビニエンスストアや銀行ATMで支払える手軽さから、地方の顧客や高齢者層なども含め、幅広い層を取りこぼさずにカバーすることができます。
スマホ決済 (PayPayなど)|日常的な利用者をストアに誘導
PayPayをはじめとするスマホ決済(QRコード決済)は、日常の買い物で利用するユーザーが急増しています。
普段から使い慣れている支払い方法がECサイトでも利用できると、顧客は安心して購入できます。特に、各スマホ決済サービスが実施するポイント還元キャンペーンなどは、新規顧客をストアに誘導するきっかけにもなり得ます。
【BtoB事業者向け】請求書払い・掛け払い決済の導入
Shopifyは個人向け(BtoC)だけでなく、法人向け(BtoB)のECサイト構築にも活用できます。
BtoB取引では、一般的なオンライン決済ではなく、「請求書払い(掛け払い)」が主流です。これは、商品を先に納品し、後日まとめて請求書で代金を支払ってもらう取引方法です。
Shopifyでこの請求書払いを実現するには、専門の決済代行サービスと連携するのが一般的です。
これらのサービスを利用すると、以下のようなメリットがあります。
- 請求業務のアウトソース:請求書の発行・送付、入金管理、督促といった煩雑な業務をすべて代行してもらえます。
- 未回収リスクの保証:取引先が倒産した場合でも、代金が100%保証されるため、安心して新規の取引先とビジネスを始められます。
- キャッシュフローの改善:売上金を早期に入金してくれるため、資金繰りが安定します。
Shopifyアプリストアで提供されているBtoB向けのアプリや、API連携に対応した決済代行サービスを活用することで、自社のBtoBビジネスに最適な決済フローを構築することが可能です。
まとめ:自社に最適な決済方法を導入して売上を最大化しよう
Shopifyの決済方法選びは、単なる機能選択ではなく、ストアの売上や利益、さらには顧客満足度に直結する重要な経営判断です。
この記事で解説したポイントを、最後に改めて確認しましょう。
- まずはShopifyペイメントから:特別な理由がない限り、取引手数料が無料になるShopifyペイメントを有効化するのが基本です。
- コストは二重構造で考える:外部決済サービスを検討する際は、サービス自体の手数料とShopifyの取引手数料を合算した「トータルコスト」で比較しましょう。
- 3つのステップで論理的に選ぶ:「①顧客層」「②トータルコスト」「③運用工数」の3つの視点から、自社に最適な組み合わせを導き出しましょう。
複雑に見えるShopifyの決済方法も、仕組みと選び方のポイントさえ押さえれば、自信を持って最適な選択ができます。
自社のビジネスと顧客に真にフィットした決済環境を整え、売上の最大化を目指しましょう。
ECサイトの構築にはECプラットフォームが欠かせません。こちらの資料では合計10社のプラットフォームの導入費用や機能について簡単に比較できるようにまとめました。
これからECサイトの構築やリプレイスを検討されているご担当者様は、こちらのボタンからECカオスマップ資料をダウンロードいただき、ぜひ比較検討にお役立てください!